「ソーシャルワーカー」と聞くと、どういうイメージがあるだろう?
病院や福祉施設、役場などで、不安や困りごとがある人の相談を聞いたり、サポートをしたり…。なんとなくそんなイメージがある。
でも、私たちが思っている以上に、「ソーシャルワーカー」の仕事は幅広いらしい。
今回お会いするのは、伊藤次郎さん。
伊藤さんは、自殺対策を行っているNPO法人OVAの代表を務めている。自殺を考えている人の相談に乗るのはもちろん、人を助けるための新しい手法を開発し、それを全国に広めていく活動をしているそう。
人を助けるための新しい手法って、どういうことだろう?
各地で研修をされているとのことなので、まずはその研修をのぞいてみることに。
テクノロジーで、相談に来られなかった人たちを援助へつなぐ

研修に集まっていたのは、行政の施設などで働いている相談援助職の方たち。
「死にたいという声って、目に見えないですよね。どうやって見つければいいんでしょう?」そんな投げかけから、研修は始まる。実は、twitterには1日15000件ほどの「死にたい」という書き込みがあり、google検索では月に24万件も「死にたい」と検索する人がいるそう。
OVAでは、そうして「死にたい」と検索した人たちに向けて、相談窓口へと案内する検索連動広告を打ち、メールやチャットで苦しんでいる人たちの相談を受け付けている。
「この手法を、『夜回り2.0(InternetGatekeeper)』と私たちは名付けました。15歳~39歳までの若年層の死因で、最も多いのが自殺です。私たちはテクノロジーを使い、マーケティング的な手法を用いて、今まで援助に繋がれなかった人たちが、繋がれるようにしています。」

確かに電話相談なんかは、家や会社などまわりに人がいるところでは話を聞かれてしまうし、少しハードルが高いかもしれない。SNSでのやりとりなどに慣れている若者の1人としては、まずインターネット上で相談できるのは画期的だなあと思う。
本当に差し迫った緊急度が高い状況も、年に数回は起こるそう。研修では、自殺を考えている人が社会的にどんな問題を抱えているかや、自殺のリスクの高い人を見つけ出す方法、相談に乗る時のポイントまで、具体的なコツがいくつも話される。

伊藤さんは、こうして研修や講演を行い、各地で普及啓発活動を続けるだけでなく、自殺願望を抱える人のオンライン相談にも自ら乗り、場合によっては相談者がいる現場まで話をききに行く。
すごいことをしているな…と尊敬する一方で、なかなか自分にはできそうもない。
なぜ伊藤さんは、こういうことができるんだろう…? 素直にそんな疑問が浮かんでしまう。
気づいちゃったから、やらなきゃいけない
事業を始めるに至った原体験について尋ねてみると、出てきたのは、高校時代の話。
「成績もよくて、部活でも部長をやってたんですけど、なんだか落ち込んで、死にたい…ってなっちゃったんです。非行に走るとか、虐待を受けたとかではないんですが、夜も眠れなかったりして。誰にも言えなかったんですけどね。」
伊藤さんが高校生だったのは、10代の犯罪が社会でニュースになっていた時期。自身の心の行きづまりもあり、彼らのことが他人事に思えなかった伊藤さんは、「非行に走る青少年を支えたい」と、警察官になることを目指したそう。ところが就活に失敗し、大学卒業後には一度フリーターに。
「進路に迷っている時、『チェンジメーカー』っていう本をたまたま見つけたんです。社会の問題をビジネスの手法で解決する人たちのことを知って、こんな人たちがいるんだ、僕もこうなりたい、と思った。」
目標を見つけた伊藤さんは、企業のメンタルヘルス対策を行う会社へと就職を決め、ビジネスでの経験も積んだ。その後、専門学校に行って精神保健福祉士の資格を取得。精神科クリニックで相談援助の経験を積んだあと、フリーランスとして独立する。
今の活動を始めたのは、独立してしばらく経った頃。
「2013年の6月に、若者の自殺が増加していると報道されて。そのニュースを聞いて、『死にたい』と検索している人に表示できるような、検索連動広告の手法を思いついたんです。すぐに広告の打ち方を勉強して、2週間後には自殺を考えている方の相談を受けるようになりました。」

思いついても実際に始めることは難しそうだけど、すぐ始められたのはなぜだったんだろう。
「すでに当時、『死にたい』って検索が一つの検索エンジンで月に13万件もあったんです。広告を打てば、その人たちと出会うことができる。やらないって選択肢はなかったんですよね。気づいちゃったからやらなきゃいけないな、って。やればやるほど、どんどん相談が増えて、こんなに困ってる人がいるのかって思いました。」
最初は仕事をしながら広告を打ち始めた伊藤さんだが、相談のボリュームが増えて、仕事は辞めることに。しばらくは無収入で、自分の貯金で広告を打ち続けながら、相談に乗る日々が続いた。
「なんでできるのか、自分でもよくわからないんです。でも、目の前に血だらけの人が倒れているとするじゃないですか。そしたら救急車呼ぶのって、自然な行為じゃないですか。モチベーションがあるとかないとかじゃなくて、やんなきゃいけないことっていうか。それが毎日起こる感じなんですよね。」

自分で事業を始めてから1年後、2014年の7月にNPOとして法人化。しかし、苦労は大きいと話す。
「最初の3年間はほとんど食えない状況でしたし、貯金は全部なくなりました。でも、失敗して貯金がゼロになったり借金したりしたとしても、そこから稼いで再起する力はあると思っていました。だから恐怖とかはなかったし、とにかくハイリスクの人たちと出会えるこの手法を広めないと…って責任を感じていました。誰も他にやっていないし、事業のマネタイズも難しい。不可能なことかもしれません。だからこそやっているという感じです。」
今は4年目になり、助成や行政委託の話も入り始め、少しずつ安定してきたそう。現在は、非常勤も含めた6人のスタッフで仕事をしている。
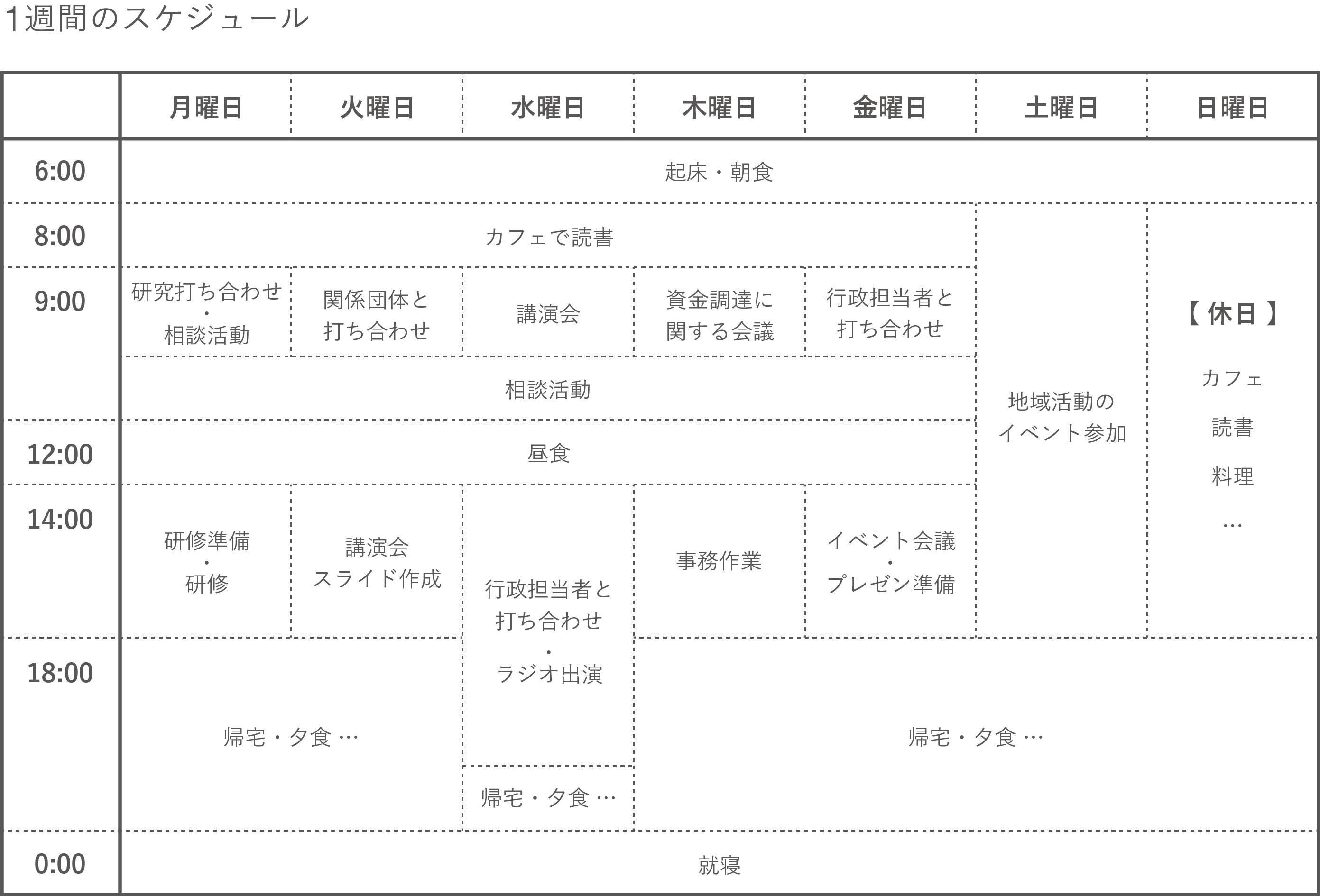
「実は、1人で事業をやり始めたとき、最初の2週間くらいで倒れました。思ったよりしんどくって、体に来ちゃったんですよね。やっぱり1人では受け止めきれないなと思って、今はチームで対応するようにしてます。スタッフも『こんなやり方で困っている人と出会えるんだ』と、夜回り2.0の手法に共感してくれている人が多いですね。」
政治や行政、社会への働きかけを含めてのソーシャルワーク
今は、そうして開発した手法を、普及啓発していく活動にも力を入れている。
「困っている人が相談に来るのをただ座って待つのではなく、困っている人がいる現場に自ら出向いていくことを、アウトリーチといいます。『夜回り2.0』も、ネットに困っている人がいるのだから、ネットに出ていこうというアウトリーチの1つ。この手法は、自殺だけではなく、他の困りごとを抱える人たちにも使えるものだと思うので、もっと横に展開していきたい。いろんな団体が当たり前にアウトリーチをやっている制度や文化をつくっていきたい。助けてと言える社会、助けてが受けとめられる社会をつくる。それが大きなビジョンですね。」
「あともう1つは、自殺対策に国としてもっと予算をつけて、ちゃんと職業にして担い手を増やしたいんです。自分は全財産払って、この活動をなんとかやってきたけれど、それって普通のことじゃないと思うんです。個人の無茶な頑張りに頼っている状態は、その人が倒れたら終わってしまう。」
「現状、自殺を考えている人の支援はボランティアの方が多くやっています。病気になれば医者、事故に遭えば救急救命士と同じように、自殺を考えている人の支援も、ボランティアではなく仕事として行っていく必要があると考えています。ボランティアに頼っている状況では、自殺を考えている人を支える担い手が増えていきません。」

伊藤さんは、理想ばかりを語っているわけではない。今までも実際に政治家にロビイング活動を行ったり、行政に提言などを行って、予算増加や新しい制度づくりに取り組んできた。
「2017年の国の自殺対策のガイドラインである自殺総合対策大綱改訂の際には、私が発起人・共同代表である『若者自殺対策全国ネットワーク』という組織で、自殺対策の更なる推進を国に訴えかけました。実際に子ども・若者の自殺対策の更なる推進が、項目として新設されています。自分や自団体でできることは限られていますから、他の人や団体とも協力関係を築いて、社会に働きかけていくことが大切だと思っています。」
要望書をみんなで取りまとめて、現状の社会が抱えるリスクなどを伝えて、政治家にロビイングしていく。
そういった活動は、一般的なソーシャルワーカーの業務とは違うように思うのだけれど、なぜ伊藤さんは、そこまで手掛けるのだろう。
「多くのソーシャルワーカーは、個人への直接支援をやっていて、困った人がどうやったらこの社会で、この地域で幸せに暮らしていけるか、一緒に考え、サポートしている。それはそれでとても重要な仕事なんです。でも、『じゃあ、困った人ってどうして困ったの』って考えてみると、社会に問題があったりするわけですよね。問題を解決するには、個人への働きかけだけじゃなく、社会や政治への働きかけも含めて、やっていく必要がある。」

「僕は、そういうのが本当のソーシャルワークのあり方だと思っているんです。当事者の方は、『問題を抱えた人』ではなくて、『社会の問題を教えてくれる人』でもある。自殺に追い込まれている人は、社会のいろんな歪みを引き受けてくれている人とも言えるわけです。変えなきゃいけないのは、その人個人じゃなくて、社会。だからこそ、ソーシャルワーカーには『ソーシャル(社会)』って言葉がついてると思います。」
伊藤さんは、ミクロだけではなく、ソーシャルワーカーの仕事をマクロなものとしても、捉えている。海外でも、個人に対するケースワークだけでなく、こうしたマクロな視点からソーシャルワークを勉強できるようになっていると聞いたことがある。
「これからソーシャルワーカーになりたい人には、新しい道を切り開いていってほしいです。既存の働く場所は、なぜお金がもらえるのか、考えてみてほしい。制度でカバーできるような困っている人もいるけれど、既存の制度ではカバーできないような、助けを求められない「声なき声」が絶対存在しているはず。そういう制度の穴を埋められるものを自分でつくっていくクリエイティブさを持ってほしいなと思っています。」

「相手のニーズや困りごとから、サービスを設計するっていうのは、ビジネスの世界だと基本です。でも、福祉や医療の世界では、援助する側の立場が強いんですよね。本当はこうしてほしいな、と困っている人が思っていても、なかなか伝えられなかったりする。だから、構造的にニーズが見えづらいということを自覚して、声なき声に想いを馳せていくなことが大事だと思います。」
自分で旗をあげたからこその、ポジティブなつながり
社会や政治にも働きかけながら、ソーシャルワークを続けている伊藤さん。大変ではあるけれど、志のある人たちとの出会いに支えられていると話す。
「自分が旗をあげてやりはじめたことで、他のNPOの代表だったり、社会的な活動をしている人たちとのつながりができました。そういう人たちの考え方には刺激を受けるし、一緒にいるとすごく幸せな気がします。社会を少しでも変えていこうとか、社会で排除されている人たちをなんとかしようとか、前向きな気持ちを持っている人たちなので。そういった人間のポジティブな部分に触れられるのは財産ですし、いろんな経験をさせてもらっています。」

施設に就職するだけでなく、自分で仕事や組織をつくっていく。新卒でいきなりそういうことを始めるのは難しそうだけれど、伊藤さんのように、最初は社会人として別のキャリアを歩んでから、チャレンジするという方法もある。
「新卒でソーシャルワーカーになる人も多いですけど、別の仕事を経験してからソーシャルワーカーになるっていうのも、とてもいいキャリアだと思います。僕も当初はビジネスってなんとなく好きじゃなかったんですが、会社に入ってみて、最新のビジネスの世界を知っていくって大事だなって思うようになりました。起業してる人のそばで働いて、経営や起業のことを勉強できたのも大きかったですね。」
伊藤さん自身、学生時代は、「ソーシャルワーカーになりたい、福祉の世界に行きたい」というような気持ちは全くなかったそう。実際、社会福祉士の国家試験に合格する人の4割ほどは、新卒ではなく、社会人経験を持つ人たちだという。
最後に、どういう人がソーシャルワーカーに向いていると思うか、聞いてみた。
「ソーシャルワーカーって、感謝されることはわりと少ないんですよ。"ありがとうが言われたくてやってます"という人だと、向かないかもしれない。この人を助けたい、なんとかしたいという気持ちは大事なんですけど、頭はクールじゃないと。心は熱く、頭はクールな人がいいのかなと思います。」

そして、こんなことも語っていた。
「自殺対策をやりたいです、というような人はなかなか出てこないので、そこは少し残念です。自殺だったり性被害だったり、受益者からお金をとるのも難しくて、事業継続も難しく、目を背けたくなるような深刻なテーマというのも社会には存在します。そういう表に出てこない人たちこそサポートが必要だったりする。そういう、表立って見えないものに想いを馳せられると、いいですよね。」
インタビューに答えながらも、スマホを頻繁にチェックしていた伊藤さん。「ごめんなさい。緊急の相談が入らないか、気になっちゃうもので」と話していた。常に気を張ってないといけない仕事でもあるだろうけれど、伊藤さんの物腰は柔らかだ。
彼のように、現場で人とも向き合いながら、新しい手法を開発し、政治や行政へも働きかけていくという在り方は、きっとソーシャルワーカーのロールモデルのひとりになると思う。
テキスト・写真 田村真菜 2017年12月21日
NPO法人OVA 伊藤 次郎(いとう じろう)
精神保健福祉士。企業のメンタルヘルスケアを行う会社でビジネスの経験を積み、専門学校を経て精神科クリニックで相談援助の経験を積んだのちに独立。2013年に自殺の現状に問題意識を持ち、それまでの経験と知識を活かしてハイリスクな人へリーチする検索連動システム「夜回り2.0」を開発した。2014年にNPO法人OVAを設立し、オンライン相談や自殺対策のための新しい制度づくりなどに取り組んでいる。
http://ova-japan.org